スタジオジブリの最新作『君たちはどう生きるか』。
公開当初から話題騒然だったのが、あの「しゃべる青サギ」です。
「え、鳥がしゃべる?え、しかも変身する?こわっ!」という衝撃の登場から、物語の最後までとにかく目が離せない存在でしたね。
今回はこの青サギの“正体”と、その象徴性について、いろんな角度からユルくもマジメに深掘りしていきます。
この記事を読むとわかること
- 青サギの正体にまつわる3つの有力説
- 青サギが象徴する“内なる不安”とは
- 宮崎駿が青サギに込めた深いメッセージ
- 思わず「なるほど!」と言いたくなる解釈が盛りだくさん
青サギ=ただの鳥じゃない!? 正体説その1:「心の不安の化身」
物語序盤から、青サギは眞人に対してしつこく話しかけ、ややストーカー気味(失礼)に絡んでくるのでした。
新しい家、新しい母、慣れない学校…その全てに馴染めず、心を閉ざしていた眞人にとって、この青サギはまさに「招かれざる客」そのものでしょう。
これは、眞人の心の不安や葛藤を象徴している存在と解釈できます。
母の死という大きな喪失感を抱え、その事実から目を背けたい眞人の心に、「お前の母は生きているぞ」と謎めいた発言を繰り返すあたり、不安定な心を的確に揺さぶる“内なる声”そのものと言えます。
サギの姿の中から不気味な顔の男が現れるビジュアルも、眞人が心の奥底に押し込めている認めたくない感情や、見て見ぬふりをしている現実の醜さを具現化した姿なのかもしれません。
正体説その2:「宮崎駿自身」説もアツい
青サギのあの独特のしつこさ、尊大な語り口、そして時折見せるコミカルで人間くさいユーモア。
これ、実は「宮崎駿監督本人の分身では?」という説が非常に有力なのです。
特に、眞人を半ば強引に“創作の世界(=下の世界)”へ引っ張り込む様は、「いいから黙ってこっちに来い!面白いものを見せてやる!」という、宮崎監督の若きクリエイターへの強烈なメッセージのようにも見えます。
そもそも、サギ男が完璧な案内人ではなく、ズル賢かったり、見栄を張ったり、意外と弱かったりする点もポイント。
これは監督が己の「クリエイターとしての矛盾」や「避けられない老い」をキャラクターに投影していると見ると、妙にしっくりくるのではないでしょうか。
正体説その3:「神話的存在」説も無視できない
青サギは、古代エジプト神話に登場する聖なる鳥“ベンヌ”に由来しているという考察もあり、これも非常に興味深い説。
ベンヌは太陽神ラーの魂の化身とされ、「死と再生」「創造」「知恵」「導き」を象徴する存在です。
ギリシャ神話の不死鳥フェニックスの原型とも言われています。

そう考えると、眞人を母の死と向き合わせ、新たな生へと歩ませるために異世界へ誘導する役割も、「神の使い」あるいは「魂の案内人」という神話的なポジションとして見事に成立します。
日本神話の八咫烏(ヤタガラス)のように、鳥が異界への案内役を担うのは、物語の普遍的な型でもあるのです。
「風切りの7番」の謎とサギ男の変化
物語中盤、眞人が作った矢によって、青サギは翼の「風切り羽の7番」を失い、うまく飛べなくなってしまいます。
この「7番目の羽根」は、眞人が初めて自らの意志で青サギ(=不安や嘘)に立ち向かい、その化けの皮を剥がした証。
これ以降、青サギは眞人を騙すことができなくなり、ある意味で「嘘をつけなくなった状態」に陥るのです。
この出来事をきっかけに、彼は眞人に対して協力的になり、利害の一致からではありますが、「友達」としての顔を見せ始めます。
これは、眞人が自身の抱える「不安」の正体と向き合ったことで、それが「信頼」できる相棒へと変化していく過程としても読み解くことができるでしょう。
青サギが象徴する“成長”と“許し”
最初はただただ不気味で胡散臭かった青サギも、物語の終盤では「こいつ、意外といいやつ…?」と感じさせる愛嬌を見せてくれます。
眞人自身が、自分の頭の傷という「悪意の証」を正直に告白し、過去と向き合い、人間的に成長していく過程とシンクロするように、青サギもまた変化していく。
この主人公とトリックスターの関係性が共に成熟していく様がとってもジブリ的で、心にじんわり来るのです。
眞人が自身の弱さや悪意を「許し」、青サギが敵対していた眞人を「友」として受け入れる。
この相互の許しこそが、二人の絆を確かなものにしたと言えるのかもしれません。

【ネタバレあり】
『君たちはどう生きるか』の感想を書きしました。
ネタバレありなので、まだ観ていない人は開かないですください。https://t.co/1ThUwIoZx1 pic.twitter.com/3KNDc7Dvwk— ジブリのせかい【非公式ファンサイト】 (@ghibli_world) July 16, 2023
この記事のまとめ
- 青サギは眞人の不安や成長を映す“鏡”のような存在
- 正体には「駿の分身説」や「神話的象徴説」など複数ある
- 青サギの変化は、眞人の内面の変化と連動している
- U:視聴者自身の「不安」や「信頼」への気づきを促す存在とも言える
おわりに
青サギって、最初は「なんだこのヤバい鳥」という印象が強かったものの、観終わる頃には妙に愛おしく、忘れがたい存在になっているから不思議。
ジブリ作品は、こうした“よくわからないけど、なぜか心に深く残る存在”を描くのが本当に巧みですね。
一筋縄ではいかない、矛盾を抱えた存在だからこそ、リアルで、魅力的に映るのかもしれません。
この記事を読んで、「あ、青サギってそういうことかも」と感じたら、ぜひもう一度映画を観返してみてください。
きっと、初回とはまったく違う青サギの姿が見えてきて、物語の深さに改めて驚かされるはずですよ!
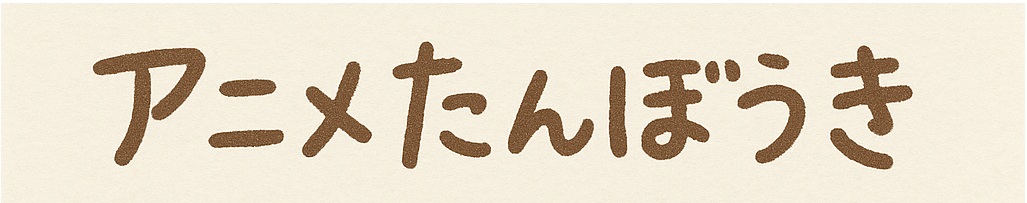



コメント